ストレスチェックとは?ビジネスパーソンに必要な制度と産業医が伝えたい活用法
- stayfitclinic

- 2025年8月27日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年11月13日
ストレスチェックは「形式的なアンケート」ではありません
こんにちは、Stay Fit Clinic院長の薮野淳也です。
働いていると毎年「ストレスチェック」を受ける案内が来る方も多いと思います。
「ただのアンケートでしょ?」と思われがちですが、実は働く人と企業を守る大切な制度です。
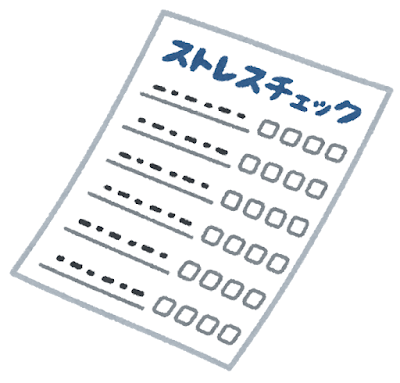
ストレスチェック制度とは?
ストレスチェックは労働安全衛生法に基づき、従業員50名以上の事業場では2015年から義務化されました。
目的は2つあります。
本人に気づきを与えること
組織全体で職場環境を改善すること
さらに、2028年度には50名未満の事業場にも義務化が拡大される予定です。現在は努力義務ですが、今から準備することが安心につながります。
チェック項目と流れ
厚生労働省推奨の「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」をもとに、以下の3点が評価されます。
仕事のストレス要因(仕事量・裁量・人間関係など)
ストレス反応(不眠・気分の落ち込み・集中力低下など)
周囲のサポート(上司や同僚に相談できるか)
高ストレス者とは?
「高ストレス者」の基準は、主に以下の2パターンに該当する人です。
ストレス反応が非常に強い(メンタル不調のリスクが高い)
ストレス要因が強く、かつ周囲のサポートが乏しい
なお、スコアが高ければ良い、という単純なものではありません。
設問によって「高いほど良い(例:サポート)」と「低いほど良い(例:ストレス反応)」があり、専門的な読み解きが必要です。
ストレスチェック結果をどう活かす?|個人と企業の視点から
個人:自分の状態に気づくきっかけに
スコアを見て「なんとなくしんどかった理由」が言語化されることもあります。
睡眠不足、イライラ、頭痛などの身体反応に気づく
自分のストレス傾向(職場要因か、家庭要因か)を把握する
「面接指導の申出」や「心療内科への相談」につながる
企業:集団分析で職場改善へ
個人結果だけで終わらず、部門別の傾向を集団分析で可視化することが重要です。
部署間でストレス傾向に差がある(例:人間関係が悪い部署 vs 良い部署)
経年比較で職場改善の成果が見える
改善提案(勤務制度の見直し、1on1導入など)の根拠にできる
健康経営や人的資本開示のエビデンスとして活用可能
産業医としても、ストレスチェックの集団分析から「リスクの高い部署」や「改善余地のある働き方」が見えてくることが多くあります。
ストレスチェックの“読み解き力”が組織の未来を変える
ストレスチェックは、単なる“義務”ではなく「職場の今の状態」を映し出す鏡です。
数字を“人の声”として読み解くことが、組織の信頼や心理的安全性の向上につながります。
特に管理職や人事部門がこの結果を正しく理解し、対話のきっかけとして活用することで、メンタルヘルス不調の予防にもつながります。
おわりに|義務だからやるのではなく、未来への問いとして活用を
ストレスチェックの結果は、職場環境や働き方を見直す“問い”です。
義務だからではなく、「よりよく働くにはどうすればいいか」を考える機会として捉えてみてください。
個人の気づきから始まり、組織改善へとつなげていくことで、ストレスチェックは真価を発揮します。
Stay Fit Clinic 院長 薮野淳也
▶ あわせて読みたい
▶ 関連リンク
働く人のパートナードクター 薮野淳也
\ サービス一覧はこちら /
\ SNSでも発信しています /
・note




コメント